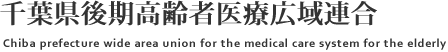保険料の算定方法

図:保険料は均等割額と所得割額の合計
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者一人ひとりの保険料を決定(賦課)します。
保険料の設定
- 保険料は、すべての被保険者一人ひとりに納めていただきます。
- 保険料の額は、被保険者一人ひとりに均等に課せられる「均等割額」と、被保険者一人ひとりの所得に保険料率を乗ずることによって算出される「所得割額」の合計額です。
- 保険料の均等割額と所得割額は、広域連合における2か年の財政運営を通じて、医療にかかる給付費の約1割をまかなえるように設定しています。この料率は、千葉県内で同一です。
保険料率について
保険料率は、都道府県ごとに決定し、2年ごとに見直すように法律で定められています。千葉県の令和6~令和7年度の保険料率は次のとおりです。
令和6~令和7年度の千葉県の保険料率
均等割額 43,800円
所得割率 9.11%※
※令和5年中の賦課のもととなる所得金額が58万円(公的年金収入額211万円相当)以下の方は、令和6年度の所得割率が8.45%となります。
保険料の算定
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が公平に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」とを合計した額をもって、対象年度1年間分(4月~翌年3月の12か月分)の保険料として算出されます。
年度の途中から後期高齢者医療に加入となった場合は、加入した月からの月割計算となります。
計算の結果、100円未満の端数がある場合には端数を切り捨てます。
保険料の賦課限度額(均等割額と所得割額の合計額についての限度額)は80万円です。(令和6年度に75歳に到達して被保険者となる方を除いて、令和6年度は73万円、令和7年度は80万円となります。)
所得の内容に応じて、算出された保険料額から金額がさらに軽減されることがあります。詳しくは「保険料額の軽減について」を参照してください。
「均等割額」は、被保険者一人ひとりに均等に課せられる額で、1年間分の金額が43,800円となります。
均等割額=43,800円
「所得割額」は、賦課のもととなる所得金額(※)に、所得割率を乗じて計算します。
所得割額= 賦課のもととなる所得金額×所得割率9.11%
※「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
なお、総所得金額等が2,400万円を超える場合は基礎控除が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がありません。
公的年金等収入と給与所得がある人は、給与所得を計算する際に、給与所得から最大で10万円を控除する所得金額調整控除の適用があります。
「賦課のもととなる所得金額」に含まれる主な所得額
総合課税分
- 公的年金所得額
- 給与所得額(専従主から支払われた給与(専従者給与)も所得として含まれます。)
- 営業所得額
- 農業所得額
- 不動産所得額
- 利子所得額(源泉分離課税で完結しないもの)
- 配当所得額(申告したもの(総合課税を選択したもの))
- 一時所得額
- 短期譲渡所得額(総合課税分)
- 長期譲渡所得額(総合課税分)
- その他雑所得額
申告分離課税分
- 短期譲渡所得額(申告分離課税分)(土地建物等の譲渡など)
- 長期譲渡所得額(申告分離課税分)(土地建物等の譲渡など)
- 山林所得額
- 先物取引に係る雑所得等の金額
- 株式等に係る譲渡所得等の金額
- 配当所得額(上場株式の配当所得など)(申告したもの(申告分離課税を選択したもの))
注意点
- 保険料の所得割額計算の対象となる「賦課のもととなる所得金額」には、退職所得、非課税所得(遺族年金・障害者年金・失業給付など)は、含まれません。また、算出上においては、「総合課税分」と「申告分離課税分」のそれぞれについて損益通算や、繰越雑損失を除く各繰越損失額・特別控除額の控除を行い、「総合課税分」「申告分離課税分」の金額を合計します(マイナスの場合は0円として合算)。
- 「賦課のもととなる所得金額」となる前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から控除できる金額は、基礎控除額43万円だけです。所得税や市町村民税(住民税)の課税所得金額のように、医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除といった各種控除は適用されません。
- 公的年金等収入と給与所得がある人は、給与所得を計算する際に、給与所得から最大で10万円を控除する所得金額調整控除の適用があります。
- 総所得金額等が2,400万円を超える場合は基礎控除が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がありません。
- 上記の保険料の所得割額の計算と、「均等割額の軽減判定」、及び「医療機関などにかかるときの医療費の自己負担割合判定」とは、その計算方法に違いがあります。詳しくはそれぞれの内容を説明している箇所を参照願います。
- 各所得の詳細な説明などについては、税務署等のホームページなどでご確認願います。
所得割額の算出について、ご不明な点がある場合は、大変お手数ですが下記のお問い合わせ先までご連絡ください。