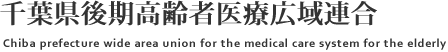医療費の自己負担割合について
医療機関にかかるときは、マイナ保険証、紙の保険証又は資格確認書を提示し、かかった医療費の一部を医療機関に被保険者本人が支払います。
医療費の自己負担割合は、原則1割負担となりますが、一定以上の所得のある被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者は、現役並み所得者(3割負担)を除き、2割負担となります。
医療費の自己負担割合は、被保険者の市町村民税課税所得(課税標準額)や被保険者の属する世帯の収入状況により判定を行い、毎年8月1日に見直されます。
医療費の自己負担割合の判定基準
自己負担割合『3割』
市町村民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者およびその方と同じ世帯にいる被保険者
○収入により、基準収入額適用申請ができる場合があります。 (詳細の条件は下記にございます。)
※出生日が昭和20年1月2日以降の被保険者および同じ世帯にいる被保険者全員の賦課のもととなる所得金額の合計が210万円以下の場合は、1割または2割となります。申請は不要です。
自己負担割合『2割』
以下の(1)(2)両方に該当する被保険者
(1)同じ世帯の被保険者の中に市町村民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる (2)同じ世帯の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する ○被保険者が1人の場合 200万円以上 ○被保険者が2人以上の場合 被保険者全員の合計が320万円以上
自己負担割合『1割』
『2割』、『3割』に該当しない被保険者
市町村民税課税所得(課税標準額)とは
市町村民税課税所得(課税標準額)とは、お住まいの市町村にて課税されている、市町村民税の税額計算のもとになる額で、この額に税率を乗じることによって市町村民税額(所得割)が決定されます。
この額は、後期高齢者医療制度の保険料算定における所得割額計算の対象となる「前年の総所得金額等」とは異なり、総合課税分、申告分離課税分それぞれの「前年の総所得金額等」から次のような各種控除を差し引き、その後、総合課税分、と申告分離課税分を合算して算出した金額です。
後期高齢者医療制度の保険料における所得割額計算の対象となる「前年の総所得金額等」については、「保険料の算定方法」を参照してください。
主な各種控除とは
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 障害者控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除(43万円)等
各種控除の詳細な説明などについては、税務署等のホームページなどでご確認願います。
注)市町村民税の課税所得金額は、所得税の課税所得金額とは違うものとなります。これは市町村民税と所得税の各種控除額に違いがあるためです。
基準収入額適用申請
3割と判定された場合でも、被保険者の属する世帯の収入状況が次のいずれかの条件を満たしているときは、広域連合に対して申請を行い、その認定を受けることで自己負担の割合が1割または2割に変わります。
(申請を受けた月の翌月初日から適用します。)
原則申請が必要ですが、お住いの市区町村で対象の方が下表の収入基準に該当することを確認できる場合は、申請不要です。お住いの市区町村と住民税を課税する市区町村が異なる等で確認できない場合は、申請が必要となります。収入金額が分かる書類をご用意の上、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課の窓口で行ってください。
世帯内の被保険者が1人の場合
| 被保険者の収入金額 | 年金収入+その他の合計所得金額 | 負担割合 |
|---|---|---|
|
383万円未満 |
200万円未満 | 1割 |
| 200万円以上 | 2割 |
世帯内の被保険者が1人、かつ被保険者本人の収入額が383万円以上で、同一世帯に70歳から74歳の方がいる場合
| 被保険者および70歳~74歳の方の合計収入金額 | 年金収入+その他の合計所得金額 | 負担割合 |
|---|---|---|
|
520万円未満 |
200万円未満 | 1割 |
| 200万円以上 | 2割 |
世帯内の被保険者が2人以上いる場合
| 被保険者の合計収入金額 | 年金収入+その他の合計所得金額 | 負担割合 |
|---|---|---|
| 520万円未満 | 320万円未満 | 1割 |
| 320万円以上 | 2割 |
収入金額とは
収入金額とは、事業所得や不動産所得、雑所得や一時所得、譲渡所得などがある場合、必要経費を控除する前の売上金額や給与及び年金収入などになります。
確定申告書(用紙のもの)では、第一表~第三表の「収入金額等」や「収入金額」の欄の額になります。
(e-Taxを利用している場合でも、入力画面中の「収入金額等」や「収入金額」の欄の額です。)
※ただし、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得について、個人住民税において申告不要を選択した場合は含まれません。
詳しいことは、こちらを参照してください。
「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第31条」(総務省運営ポータルサイトへのリンク)<外部リンク>
関連リンク