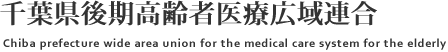自己負担限度額と標準負担額について
自己負担限度額・標準負担額とは
- 自己負担限度額
ひと月ごとにかかる医療費の限度額のことを自己負担限度額といいます。
前年(1~7月は前々年)の収入や、所得金額などに応じて世帯ごとに所得区分を判定し、その所得区分ごとに自己負担限度額が決まります。
自己負担限度額を超えて支払った医療費は後ほど(4~5か月後)高額療養費として給付されます。
所得区分の判定方法につきましては以下のリンクをご覧ください
所得区分
自己負担限度額につきましては以下のリンクをご覧ください。
高額療養費
- 標準負担額
入院した際の食事代や居住費にかかる費用のことを標準負担額といいます。
自己負担限度額と同様に世帯ごとの所得区分を判定し、その所得区分ごとに標準負担額が決まります。
標準負担額は原則遡って支給されませんので、資格確認書をお持ちの方は入院される前にお住まいの市(区)町村へ申請をお願いします。
標準負担額につきましては以下のリンクをご覧ください。
入院時食事療養費
※自己負担限度額・標準負担額はマイナ保険証を利用すれば医療機関等で確認されるため、限度額を超える支払いが免除されます。
区分Ⅱの方で長期入院(91日以上)該当の方
所得区分が区分Ⅱの方の入院日数が、過去12か月において合計91日以上となったときは「区分Ⅱ(長期入院該当)」の申請をすることで、入院時の食事代が減額されます。
※マイナ保険証の有無に関わらず申請が必要になりますのでご注意ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
区分Ⅱ(長期入院該当)の届け出について
自己負担限度額・標準負担額を資格確認書に記載する申請方法
申請により所得区分を記載した資格確認書を交付いたします。
お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当課の窓口で、以下のものをご用意の上、申請してください。
- 資格確認書
- 老齢福祉年金を受給されている方は、その年金証書や振込通知書など
- 本人のマイナンバー(個人番号)が確認できる通知カード等と申請者の身分証明書
※他の保険で交付されていた場合でも、千葉県の後期高齢者医療制度に加入した時には、改めて申請が必要です。
医療機関等での確認の受け方
マイナ保険証をお持ちの方
医療機関の受付時に情報提供に同意することで限度額を超える支払いが免除されます。
※令和7年7月31日までに限り、住所や所得区分に変更がある方のうち、令和6年8月1日以降に従前の各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ所得区分を記載した方を含む)、申請によらず、所得区分を記載した資格確認書を送付します。
マイナ保険証をお持ちでない方
オンライン資格確認の仕組みにより、事前の申請によらず病院窓口で本人同意をすることで、支払いを限度額までにすることができます。
しかし、一部の医療機関において、所得区分の提示を求められる場合があるため、所得区分の記載された資格確認書が必要な場合は、市区町村窓口へ申請してください。
※所得区分の変更や有効期限が切れる方について、令和6年8月1日以降に従前の各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ所得区分を記載した方を含む)、申請によらず、所得区分を記載した資格確認書を送付します。
医療機関等の窓口で自己負担限度額・標準負担額の所得区分が確認できない場合
医療機関等の窓口で精算される際に負担割合に応じて以下の扱いになりますのでご注意ください。
ただし、自己負担限度額を超えてお支払いされた分は、申請により高額療養費として支給を受けることができます。
(超過分は、4~5か月後に払い戻されます。また、標準負担額(入院時の食事代や居住費など)の払い戻しは、原則としてありません。)
| 負担割合 | 自己負担限度額の扱い(※1) | 標準負担額の扱い(※2) |
|---|---|---|
| 1割 | 一般1 | 現役並み所得者・一般 |
| 2割 | 一般2 | |
| 3割 | 現役並み所得者3 |
※1 自己負担限度額については、こちらのページをご覧ください。
※2 標準負担額については、こちらのページをご覧ください。